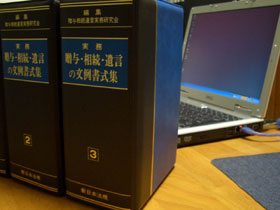|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
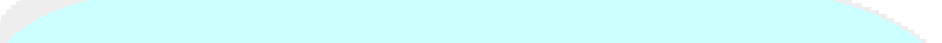 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
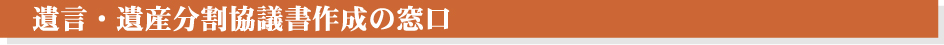 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
▼ 遺言書の種類と書き方 ▼ 遺言の執行 ▼ 相続について ▼ 法定遺留分 ▼ 相続の承認・放棄 ▼ 遺産の分割
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
誰でも自分の死については考えたくはありません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
そのため遺言書を書くこと自体が「縁起でもない」ことのように思われがちです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また「遺言するほどの財産は持っていない」や「家族でちゃんと分け合うだろう」と思って遺言を残さな |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
いことも多いようです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
しかし、仲の良かった兄弟姉妹が親の遺産相続をめぐり骨肉の争いを行うことは、けっして珍しいことで |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
はありません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
これは、財産の多い少ないにかかわりません。貰えるものは少しでも多く貰いたいと思うのも、また人情 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なのです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自分の死後の話とはいえ、残った家族が争い、憎み合うことは大変悲しいことです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遺言はそんな紛争を予防し、死後において本人の意思を伝える大切な手段なのです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遺言は、本人の死後に本人の意思を伝えるという性格上、内容をあらためて本人に確認をすることができません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のため「口頭」で遺言を残しても法的には効果はありません。「証書」いわゆる「遺言書」によって残さなくてはならないのです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また「遺言書」は、法律によりその方式が厳格に決められています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法律に合致しない遺言書は効力が認められませんので、十分な注意が必要です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遺言は民法により「普通の方式」による遺言と「特別の方式」による遺言がありますが、ここでは「普通の方式」の「自筆証書遺言」と「公正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
証書遺言」について説明します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)自筆証書遺言 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
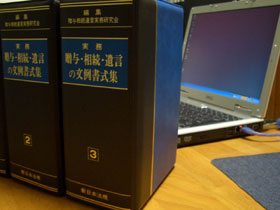 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一番簡単に残せる方式です。ただし、民法では次のように規定され、この要件が一つで |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
も欠けると法的効力をもちません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(民法968条) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
に印を押さなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
を生じない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
つまり、自書の必要があるので、パソコンで印字したものでは認められません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また、必ず日付と自分の氏名を書いておかなくてはなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
そして押印をします。押印は必ずしも実印である必要はありません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
訂正がある場合は、その場所を分かるようにして、変更したことを記入し、署名した上で、変更箇所に押印します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)公正証書遺言 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自筆証書遺言は簡単に残せる方式ですが、後に記すように遺言の執行段階において、家庭裁判所に「検認」を請求する必要があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公正証書遺言はその必要がなく、そのまま執行にすることができます。公正証書遺言は民法において、次にようになっています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(民法969条) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)証人2人以上の立会いがあること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5)公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公正証書遺言を行うには公証人(公証役場)に依頼する必要があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また、証人が2名必要です。ただし、未成年者や推定相続人、受遺者、またこれらの配偶者、直系血族などは証人となることができません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「普通の方式」の遺言には、そのほかに「秘密証書遺言」があります。なお、遺言は15歳未満の者は行えません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また、二人以上の者が同一の証書によって残すことはできません。夫婦連名で1通の遺言書を作っても効力がないのです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また、遺言は生前、いつでも自由に新たな遺言によってその一部または全部を撤回できます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
被相続人が亡くなった場合、遺言書を保管している者又は遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
検認とは遺言書が被相続人が書いたものに間違いないかを確認する手続です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また、封印してある遺言書は家庭裁判所において開封しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なお、前述したように「公正証書遺言」の場合は、公証人によりすでに真正のものと証明されていますので、検認は不要です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この検認を受けずに遺言を執行したり、勝手に遺言書を開封したりすると処罰の対象となることがあります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
被相続人はあらかじめ、遺言によって「遺言執行人」を指定するか、指定を第三者に委託することができます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利害関係人だけでは、遺言の執行段階で紛争が起きる可能性もあります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利害関係を有しない、法律の専門家を遺言執行人に指定しておくのが最善でしょう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また、指定がないときは、利害関係人は家庭裁判所に選任を請求できます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相続について、遺言書がある場合は、原則その遺言に従って遺産を分割しますが、遺言書がない場合はどうなるのでしょう? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その場合は「法定相続人」に法定の割合で相続の権利と義務が生じます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「法定相続人」の相続順位と相続割合は次のとおりです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※相続順位(相続順位の上位の者がいない場合に下位の者が相続人となります)
|
1
|
子
|
代襲相続あり(子が既に死亡している場合はその子が相続) |
1/2
|
|
2
|
直系尊属
|
父母・祖父母等 |
1/3
|
|
3
|
兄弟姉妹
|
代襲相続あり(相続者が既に死亡している場合はその子が相続) |
1/4
|
|
※
|
配 偶 者
|
配偶者は常に相続人となる(共同相続する者の残りの割合) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*代襲相続=相続人が相続前に死亡している場合その子が代わって相続すること |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*直系尊属=親・子等、縦の関係を直系といい、兄弟姉妹等、横の関係を傍系という。また親、祖父母等、上の関係を尊属、子、孫等、下の関係を卑属という |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*嫡 出 子 =婚姻関係にある男女間に生まれた子。婚姻関係にない男女間の子を非嫡出子という |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配偶者は常に相続人となります。婚姻関係にない内縁関係の場合は相続権がありません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たとえば、配偶者とは別居をしていて、別の者と生活を共にしていても、相続権は配偶者にあります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ただし、配偶者以外の女性に被相続人の子がある場合は、その子には相続権があります(嫡出子の1/2)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
子は実子、養子の区別はありません。養子も実子と同じ相続権があります。また、養子は実親、養親の双方に対して相続権があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相続の割合は子と配偶者が相続する場合は子が1/2、配偶者1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直系尊属と配偶者の場合は直系尊属1/3、配偶者2/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
兄弟姉妹と配偶者の場合は、兄弟姉妹1/4、配偶者3/4となります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
例えば、遺産が1,000万円あり、相続人が配偶者、嫡出子2名、非嫡出子1名の場合は、配偶者に1/2の500万円、子3人に1/2の500万円となりま |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
す。そして、非嫡出子は嫡出子の1/2の相続分となりますので、嫡出子2名に200万円ずつ、非嫡出子に100万円の割合で相続となります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分の権利をもつ遺留分権利者となります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遺留分とは、遺言による遺贈や生前の贈与(相続開始前1年間分)によっても侵害することのできない一定割合のことです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遺留分は… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*直系尊属のみの場合 = 被相続人の財産の1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*その他の場合 = 被相続人の財産の1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
となり、その遺留分を法定相続分により分割することになります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
例えば、6,000万円の財産を持つ被相続人が、遺言に「内縁関係にある女性に全て財産を譲り、別居中の妻と子には残さない」旨を記し、亡く |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なったとします。妻と子がこの遺言の内容を知っても異議を唱えなければ、遺言の通りになりますが、法定の遺留分を主張することもできます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この場合は、妻と子で全体の1/2の3,000万円が遺留分となります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
さらに妻と子の間では法定相続分の1/2ずつとなり、妻が1,500万円、子が1,500万円、子が3人いれば子は500万円ずつとなります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
もし、妻と直系尊属が相続人の場合は、妻は2/3の2,000万円、直系尊属が1,000万円という計算になります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なお、遺留分の減殺請求は、権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った日から1年、相続開始の時から10年以内に行わ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なければなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「相続」にはプラスの財産はもちろんですが、借金や負債などのマイナス財産も含まれます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
そのため、時として遺産を相続したら借金の方が多かった…などの事態も起きうるのです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この場合は、借金の返済の義務が相続人に生じます。では、その借金は必ず相続しなければいけないのでしょうか? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民法では、相続の「承認」または「放棄」という手続を設けています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相続を承認して被相続人の権利義務を引き受けるか、権利義務を放棄するかを選択できる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
わけです。承認には単純承認と限定承認の2種類があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この承認(限定承認)または放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時か |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ら3箇月以内」に「家庭裁判所」で行わなければなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行われなかった場合は(単純)承認をしたことになります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先述のように相続財産より借金の方が多いような場合は、相続の放棄か限定承認をするこ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
とにより、債務を負わなくて済むようになります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)単純承認 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無限に被相続人の権利義務を承継しますので、負債も承継することになります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「相続の承認又は放棄をすべき期間」に限定承認または放棄を行わなかった場合は単純承 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
認したことになります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)限定承認 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を負います。認したことになります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相続人が数人いるときは、共同相続人の全員が共同して行わなくてはなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「相続の承認又は放棄をすべき期間」内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)放棄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初めから相続人にならなかったものとみなされます。家庭裁判所に放棄の申述しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「遺産分割協議」で「○○が遺産の全てを相続する」旨の協議が整ったので、自分は放棄したと思いこんでいる人がいますが、これは、あくまで |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
も分割上「自分はいらない」と言っているだけで、民法上の放棄ではありません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
もちろん、勝手に「財産は一切いらないから借金も負わない」と主張していても放棄に該当しません。あくまで、家庭裁判所に放棄の申述をする |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必要があるので、要注意です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この点を注意しないと、自分では「放棄」したつもりでも、期間が経過してしまえば単純相続したことになり、気が付けば債務を負っていたとい |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
うことにもなりかねません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※承認・放棄した場合、「相続の承認又は放棄をすべき期間」内であっても撤回することはできませんので注意が必要です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遺産の分割方法には「指定分割」「協議分割」「審判による分割」があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「指定分割」とは、前述した被相続人による遺言によって指定されるものです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遺言が無い場合、かつ相続人が複数いる場合は共同相続人の協議によって分割します。これを「協議分割」といい、協議は全共同相続人が参加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
し、合意しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この際に作成するのが、いわゆる「遺産分割協議書」です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また、全共同相続人が簡単に判明する場合はよいですが、相続関係が複雑で相続人そのものを探さなくてはならない場合もあります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「遺産分割協議書」の作成や「相続人調査」は専門家に依頼することをオススメします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
協議による分割で、協議が調わなかった場合は、家庭裁判所に審判を請求します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相続人のうち行方不明の者がいる場合も、全共同相続人が揃わないわけですから、当然に家庭裁判所に審判を請求しなくてはなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
請求は1人で、または共同で行うことができます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当事務所では、遺産分割協議書の作成を通して相続人のご相談を承っています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また、相続登記が必要な場合には司法書士による登記手続きのお手伝いもいたします。相続に関することは当事務所へご相談ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※法律上、相続に関する紛争解決に直接関与することはできませんので、ご了承ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電子定款・内容証明・車庫証明・自動車登録・公正証書・離婚協議書・遺産分割協議書・成年後見・会社設立・法人設立
|
|
|
|
行政書士廣澤事務所・長野市
|
|
|
|
Copyright(C) 2006 Hirosawa Office All rights reserved
|
|