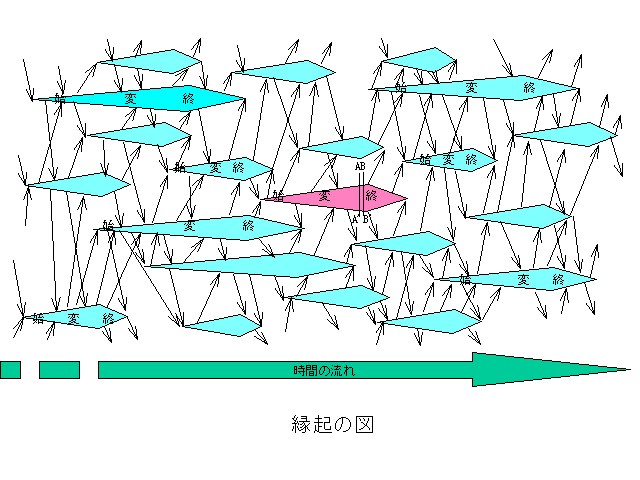
(2000年10月)
前段階として、まず縁起についてまとめたい。私の解釈だけを述べてミスリードしてしまってはまずいので、仏教の歴史におけるいくつかの縁起の解釈をまず荒っぽく振り返っておく。
最初期の経典に残る縁起(的な表現)は、ほとんどが苦の分析であり、苦の根拠の追求を目指している。「縁起」(paticca-samuppada=縁って起こること)という 後に統一的に使われる術語もほとんど現れず、原因(nidana)、因(hetu)その他の様々な言葉をその時その時で不統一に用いて縁起「的」な事柄を表現している。あるいは、それらの言葉さえ使わずに名詞の格変化(奪格)のみによって原因を表現しているケースも多い。
すなわち、
「Aを因として、B(様々な苦)がある。」
「Aから(奪格)Bがある。」
といった形式である。この段階では、具体的な苦の原因A(執着、触、など)と、その結果としての苦B(憂い、不快、争い、など)をほぼ常に伴っており、原則的には一因一果の一方通行の形式である。
その後、苦の原因追求は、次第に深まり、精緻になり、統一化され、縁起「説」と呼べる段階に至り、一因一果の有支縁起を鎖のように連ねていき、やがて十二支縁起が完成する。(十二支縁起は仏滅100年後といわれる上座部・大衆部の根本分裂の時には既に完成していたようであるから、釈尊からそう遠くない。)あわせて「縁起」(paticca-samuppada)や「此縁性」(idappaccayata)といった述語も確立され、「支」を捨象した縁起の抽象化も始まる。すなわち、
これがある時、かれがある。これが生ずる時、かれが生ずる。これがない時、かれがない。これが滅する時、かれが滅する。
という定型句がそれである。古い時代には具体的因と果の組合わせで言い表してきた事を、「これ」と「かれ」に抽象化して言い表すことが始まった。
時を経て、大乗仏教、特に中観派において、無我・縁起の考察は研ぎ澄まされ、かつての因→果の一方通行の素朴な縁起観から、論理的ともいえる相依性の縁起観にまで発展(逸脱?)する。たとえば、「親を因として子が産まれる」が素朴な形だとすると、中観では「子がなければ、親は親たり得ない。親は子に依って親となる」といった論理も展開し始める。(無時間的・相依的縁起)
このような縁起の捉え方は、一面で言葉を問題にする事でもあり、中観派は言葉に関する考察も深めていく。
縁起説は、中国でさらなる発展(逸脱?)を遂げ、華厳の重々無尽の法界縁起に行き着く。世界中のあらゆる現象は互いに縁起し合い、浸透しあい、一微塵の中にすべてが包摂され、相即相入、事事無礙、云々という世界観である。無時間的・空間的・多因多果のネットワーク的縁起といえるだろうか。(正直に言うと、よく分かっていないので、ごまかして書いている。私のイメージでは、インターネットの説明図でよくみる、たくさんのPCがWeb上でつながって情報をやり取りしているような感じ。安直か? 中国仏教については、まじめに取り組めていないので、ご容赦を)
以上、いくつかの特徴的な縁起説のタイプを独断的に選んでざっと説明した。縁起説の大まかな展開の道筋は承知して頂けたと思う。
釈尊御自身の縁起について想像すると、釈尊は十二支縁起を悟られた、とするのが仏教の伝統であるし、古い経典(ウダーナ、律蔵など)にもそのように記述されている。けれども、文献学的研究によれば、釈尊御自身は、縁起(paticca-samuppada)という言葉そのものはおそらくは用いておられなかったようだ。(アルファベットで書き写したのはパーリ語である。釈尊はマガダ語で話しておられたと考えられるが、何語にせよ、「縁起」を術語化して、明確に対象化してはおられなかったと思われる。)
しかし、次のような記述もある。(曽我による要約)
初転法輪で、釈尊から中道と四聖諦(苦集滅道)を説かれた五比丘の一人コンダンニャは「集法であるものはすべて滅法である」(遠塵離垢の法眼)との見解を得て最初に悟った。(パーリ「律蔵」、相応部「初転法輪経」)
釈尊の直弟子中最も重要な人物、サーリプッタ(後に作られたおなじみの般若心経に登場する舎利子)がサンジャヤ(六師外道のひとり)の元を離れて釈尊の元へ出家したきっかけは、五比丘のひとりアッサジによる釈尊の教えのためらいながらの要約、「諸法は因より生じる。如来はそれらの因を説く。また、それらの滅をも。偉大な修行者はこの様に説く」(縁起法頌)であった。(パーリ「律蔵」)
このように仏教史の重要なポイントで縁起的な見解がキイとして働いている。四聖諦の「集」(苦には原因がある)も「滅」(その原因をなくす事によって苦もなくすことができる)もすでに十分縁起的であると私は思う。
また、たとえば三枝充悳「初期仏教の思想」(下)第9章を見ても分かるとおり、初期経典に残る縁起的表現のおびただしい数をみても、釈尊にとっても縁起(的発想)は、教え・悟りの中心であったと考えて間違いない。
以上、仏教史における縁起説の変化・発展(逸脱)の流れと、縁起説が一貫して教えの重要な柱であった事を見た。
次に私自身の縁起解釈をまとめてみる。
この図を見て頂きたい。(実ははじめてパソコン上で作った図である。)
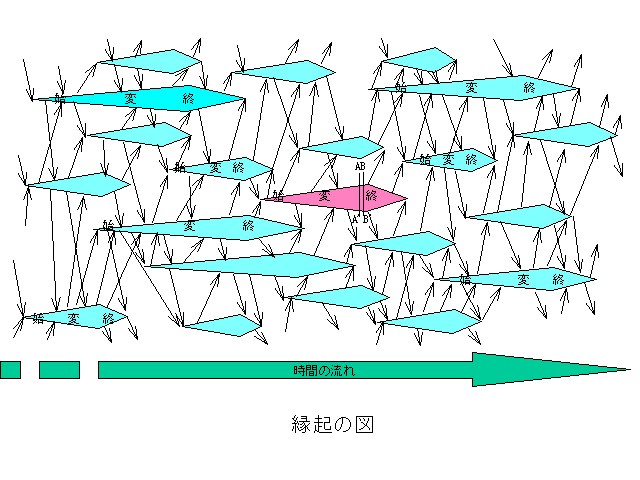
菱形は、現象を示している。「法」だとか「行」といった仏教用語を使えば仏教学的で格好がいいけれど、様々にひねくり回され色をつけられた用語であるため、かえってややこしい議論に陥りかねない。さしあたり、さらりと「現象」としておきたい。
「現象」とは、とりあえずは「存在」に対立する言葉である。つまり、存在は、「自性を持ち持続的に自存的に存在し続けるもの」ととらえられているものであり、対して現象とは、「条件によって生まれ、常に条件によって変化し続け、条件によっていつか必ず終息する出来事」である。存在と現象とは、一応は対立する概念であるが、それは、実は我々の側の見方の問題に過ぎない。存在と捉えているものも、本当は現象である。不動の巨岩も、無限の過去からそこにあった訳ではなく、よく見れば、今も風化その他の影響を受け続けており、ひび割れ、削られ、いつか砂になる。いかなる存在も、詳細に観察すれば、生まれ常に変化しいつか終わる現象である。
勿論「存在」だけが現象ではない。自然現象や歴史的社会的な事象も現象である。
あらゆる現象は、周囲の様々な現象から様々な影響を受け、変化を繰り返している。そして、さらにその変化が、周囲のいくつもの現象に多様な影響を与える。様々な縁が重なり合って、変化を生み、その変化が、また多くの現象に影響を与える。
図の矢印は、原因から結果への縁起の関係を示している。
縁起は、時間の流れの中にあり、常に時の流れに沿った方向で働く。時間をさかのぼる縁起はありえない。また、縁起は、常にひとつの現象から隣接した現象への影響であって、時空を飛び越えてかなたの現象に直接働く事はない。
たとえば、我々は釈尊に教えられている。しかし、残念ながら直接釈尊の教えに触れているのではない。古の釈尊の言葉は、人から人へと伝えられ、解釈され、文字にされ、写され、加筆され、運ばれ、翻訳され、発掘され、分析され、検討され、出版されてきた。そしてやっと今、我々は釈尊の教えの結果を学ぶ事ができる。テレビのように、かなたの情報が瞬時に伝えられる場合でも、そこには電波信号という現象が介在している。縁起は、時間的空間的に隣接する現象にしか作用しない。しかし、それがドミノ倒しのように連鎖し、分岐し、遠く広く長く影響を及ぼす事もある。
はじめに述べた仏教史上のいくつかの縁起説と比較して述べれば、私は縁起を、初期仏教のように苦の原因の追求として考えるだけではなく、広くあらゆる現象が縁によって生成・変化・消失している有り様の説明として考えている。なぜなら、執着のあらゆる対象(自分という対象も含む)が無我なる縁起の現象であり、壊法であることを知って、執着を吹き消すよすがとなるから。そして、このようにあらゆる現象を縁起の関係の中でとらえると、縁起は、一因一果ではなく、多因多果の関係となる。
中観については、無我・縁起・空をあくまで徹底し、あらゆる実体化を否定していく姿勢に、共感を感じている。というより、わたしは、中観派の無我・縁起・空に一番影響を受けている。いまだ仮説であって、正しく理解しているという自信はないが、、、。
ただ、中観の「右は左によって右たり得る」といった関係性に関する問題意識は、言葉の問題として縁起とは別に考えたいと思う。いきなりそこまで問題を拡大すると、躓きの石となりかねない。さしあたって、縁起は原因から結果への時間的関係に限定しておきたい。
法界縁起については、個々の現象を捨象して、個々の現象を超えたものを想定する悪しき発想を導くものではないかと警戒している。<縁起や法界や真如こそが、海のごとく実体としてあり、個々の現象はその波にすぎず、波を無視して海さえとらえればよい>という発想につながりかねない。
縁起は、あくまで現象から現象への関係である。関係についての概念である。paticca-samuppadaとは、縁って起こる「こと」であって、存在ではない。波のない海はあり得るかも知れないが、現象のない縁起はあり得ない。
中国・華厳に留まらず、インドの部派仏教の時代から、涅槃や虚空や真如は無為法であるという主張がなされてきた。無為法とは、縁起に寄らない、自存的恒久不変な存在という意味である。わたしは、これらの「無為法」は、抽象概念にすぎず、現実の存在ではないと考える。抽象概念を絶対的「存在」に祭り上げることがそもそも執着である。そういう操作によって、現実に現象している有情の苦しみを捨象し、ありもしない「絶対の無為法」を褒め称えて泰然自若、みずからの煩悩には寛大な態度が可能になる。そのような似非「仏教」を生み出す元凶が、無為法という概念であり、さらにそこから派生してくる真如や法界や縁起の実体視だと思う。言葉による実体妄想の罠には気をつけなければならない。
いかがだろう? これが私の縁起観だ。長々と書いたが、よく読んで頂ければ、まったく常識的ではないだろうか。退屈なくらい「あたりまえ」かもしれない。無用に神秘化したり、けむに巻いたりすることは、あってはならない。世俗的なレベルから釈尊の勝義をめざすのが正しい方便だと思う。
すべては縁起による無我なる現象であり無常であるということは、分別知・戯論のレベルでは理解して頂けたと思う。というより、これはまさしくあたりまえのことだ。にもかかわらず、我々は、現象を「存在」視して執着し、その執着を縁として、苦を作り出してしまう。何故そうなってしまうのか?
図のピンクの菱形は、自分という現象を示している。あらゆる現象と等しく縁起しあう無我なる現象にして、次々と執着を引き起こす自己とは、いかなる現象であるのだろうか?
次回は、図のA−A'、B−B'の間のそのつどの自己を切り出し、図で考えてみたい。
私が自分の縁起観を作り上げるのにどこからどんな縁を受けたかは、もはや自分でも分からないが、今回この一文を書く時は、下記の書物を所々参照した。
中村元選集(決定版) 第11巻「ゴータマ・ブッタ I 」 春秋社
平川彰著作集 第1巻 「法と縁起」 春秋社
三枝充悳 「初期仏教の思想」(下) レグルス文庫
同 「縁起の思想」 法蔵館
縁起理解を、時間的解釈か空間的解釈かで区分するという視点は、松本史朗先生の影響である。
ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
soga@dia.janis.or.jp
曽我逸郎