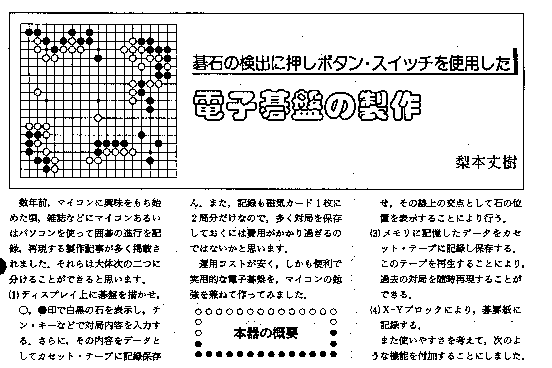 |
 |
 |
開発の経緯
|
昭和50年代の初め頃からワンボードマイコンが出回り出した。囲碁の棋譜記録は、石の打った位置を座標として表しているので、コンピュータで扱うのには都合が良い。 |
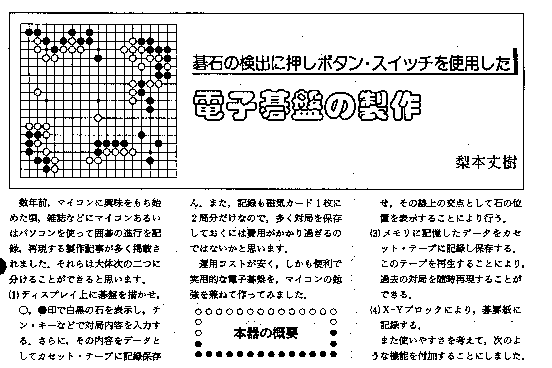 |
 |
 |
| 上図は雑誌「トランジスタ技術」の昭和62年(1987年)11月号に掲載された記事の一部である。写真に見られるように、手製品であると云うこと、石を置いた時の検出法が原始的な方法であると云うこと等で、実用向きではなかった。 |
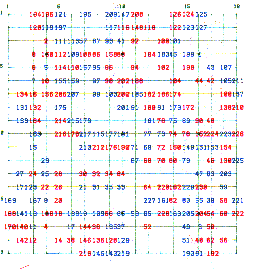 |
普通の棋譜と同じく碁罫紙に記入する形式をとりたかったので、プロッタを使って印刷した棋譜。テレビ碁などを見ながら石を置いて行くと、中のメモリに自動的にその位置が記録される。 データは製作した碁盤から直接、カセットテープレコーダに保存する。 |
 |
 |
|
〇引き続いて携帯用の棋譜記録機を製作、同じく平成元年(1989年)2月号に掲載された。 1から19までの押しボタンスイッチを2回押すことによって石の置かれた位置を表す。その時、縦横に並んでいるLEDが押しボタンスイッチに対応して点灯するので、入力を確認することが出来る。 |
| その後、20手くらい打つ毎にデジタルカメラで撮影し、それを入力順序が分かるものは数字で表し、あとはグループ入力として扱う方法などを検討していた。 2年程前にCPUのZ80が周辺ファミリのチップを含めて小型のボードになっているのを知り、上記の棋譜記録機を携帯に便利なよう可能な限り小型化して製作したのが次の写真である。 |
 |
スペースの関係でLEDを縦横に配置出来なかった。2列に並んでいるLEDの左側が縦座標、右側が横座標にそれぞれ対応する。 プログラムは10年前のものと基本的には同じである。 |
 |
ボタンを押した時の表示をLEDから7セグメントLEDに変更したもの。大きさは上のものと同じである。 表示を液晶にしたり、配線をプリント基板化したりすれば、少なくとも高さはこの半分以下にすることが出来るのではないかと思うが、素人ではこの辺が小型化の限界である。 |
|
|
| (棋譜記録機の市販品) | (この項 開発の経緯) | ||||||||